WELLNESS INVESTMENT CLUBのtoshiです。
人間は誰でも、体の中に百人の名医を持っている
ヒポクラテス
食べ物で治せない病気は、医者でも治せない
これは、紀元前400年頃に生き、医学の父と呼ばれるヒポクラテスの箴言である。
3分で世界の見え方が変わる。
現代は見えざる格差が着実に拡がっている時代であるという。
そして、その見えざる格差とは?
「健康格差」
である。
そして、「健康上流」に位置するためには、健康リテラシーを高め、日々の習慣に落とし込む必要があるのである。
そんな健康格差社会で生き抜く処方箋となる本をご紹介する。
それでは、本日のthree minutes investmentはこちら。
アイザック・H・ジョーンズ氏の『超一流の食術』である。
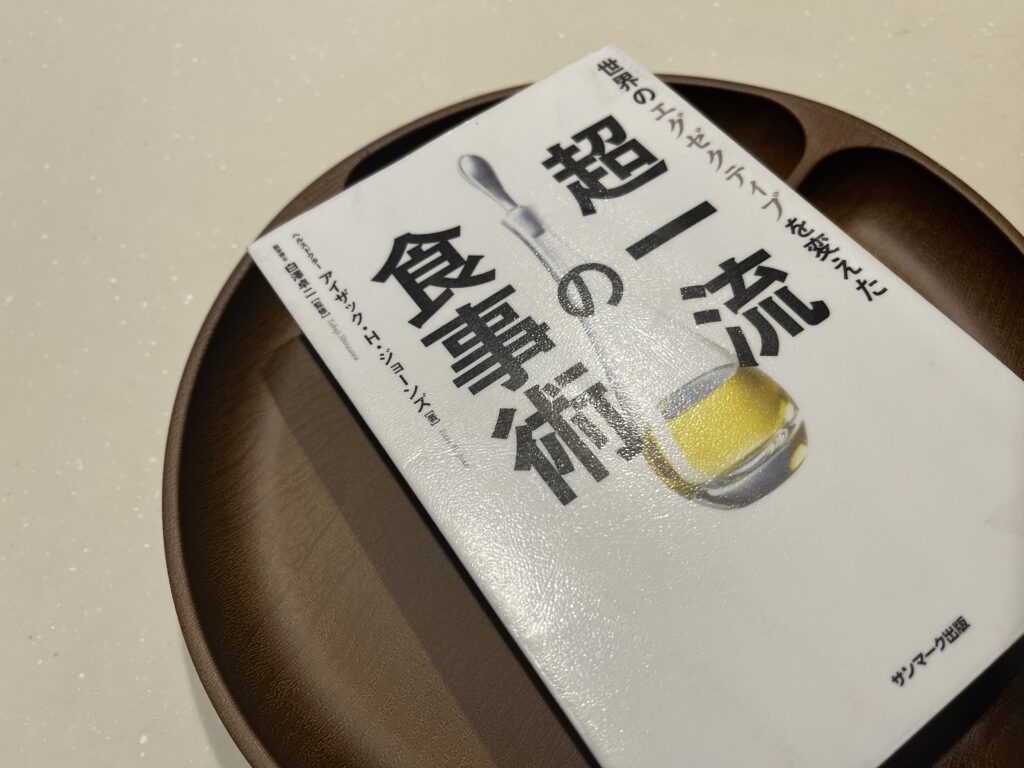
「良いアブラ」を摂れば奇跡が起きる
まず、いちばんはじめに結論を述べてしまおう。
忙しい人はここだけ、見てもらって、頭に暗記してもらえれば、最低限はそれで十分である。
それは、
「糖質を控え、健康的な脂質=「良いアブラ」を摂る」
以上である。
それだけで、疲れにくく、病気を寄せつけず、太らず、健康的で若々しく、しかも脳がクリアに機能するハイパフォーマンスな人生が手に入るのである。
筆者はファンクショナルメディスン(機能性医学)の医師として、世界のエグゼクティブたちに健康や予防医学、アンチエイジングのプログラムの提供を通して、ビジネスや人生においてのパフォーマンスを最大限に向上させる手伝いをしており、多大なる結果を出している。
そして、そんな筆者自身は、ティーンエイジャーの頃は「発達障害」の診断を受け、特別クラスに在籍していたという。
当時の自分を振り返ってみると、いつも世界に〝もや〟がかかっているような感覚だったという。
何かをやろうとしても、数分間も根気が続かない。
頭の中は常にぼんやりしていた。
そんな時にある転機が訪れた。
ある自然療法の医師のもと、健康的な食事に切り替えたところ、みるみる体調に変化があらわれ始めたのである。
その医師が特に強調したのは、次の2点。
まず、
「砂糖」を控えること
そして、
「良いアブラ」を積極的に摂ること
次第に、頭の中にかかっていた〝もや〟がスーッと消えて、世界がクリアに把握できるようになってきたという。
その後、たった4ヶ月で特別クラスから普通クラスへと移り、成績も「オールA」に変わっていったというから驚きである。
その後、大学院を主席で卒業し、今は様々な経験を積みながら、グローバルに活動の場を広げていっているのである。
まさに「奇跡」である。
「良いアブラ」を摂ることで奇跡が起こる過程で、カラダの中では何が起きているのであろうか?
「シュガーバーニング」から「ファットバーニング」へ
それは、糖質をエネルギー源として使う「シュガーバーニング」(糖質燃焼型)の状態から、脂質をエネルギー源として使う「ファットバーニング」(脂質燃焼型)の状態に自分の体をつくり変えていくことを意味するのである。
私たちのカラダは、本来、約400万年もの間、「ファットバーニング」で生活してきており、体質的にカラダはそれに合わせて作られているのである。
穀物を栽培して、その糖質からエネルギーを得るようになったのは、今からたった1万年前のことなのである。
人類史的にカラダはまだまだ、「シュガーバーニング」には適していないのである。
糖質の燃料タンクは、すぐに燃料を取り出せるというメリットの反面、最高でもおよそ2000キロカロリーしか蓄えることが出来ない。
ちょっと運動すれば、あっという間に空になってしまう量である。
一方、脂質の燃料タンクのほうは、なんとおよそ4万キロカロリーも貯蔵できる。
その容量は糖質の約20倍にも及ぶ。
かつての人類は、いつ糖質にありつけるかわからなかったので、食料があるときに食べられるだけ食べて、ありったけの燃料に変え、巨大な脂質の燃料タンクに蓄えて、それを少しずつ使って生き延びていたのである。
普段は、「ファットバーニング」のシステムを使って燃料を補給し、緊急時、例えば獲物を追いかけたり、猛獣からにげたりするときだけ「シュガーバーニング」のシステムに切り替える、といったイメージで生きてきたのである。
それが現代では、糖質が容易に手に入る時代である。
キャパシティの少ない糖質の燃料タンクだけで、十分にまかなっていけるようになり、本来サブであった糖質タンクがメインになってしまったが故に、生活習慣病をはじめ、がん、脳卒中、心疾患、他にもさまざまな疾患や弊害が生じているのである。
様々な研究により、「シュガーバーニング」ではなく、「ファットバーニング」が人間のカラダに適していることは、今やアメリカの医学界では常識になりつつあるという。
糖質の〝甘い誘惑〟にだまされるな!
現代は、食料事情が果てしなく向上し、飽食の時代であり、これまでにないほど大量の糖質を摂る生活を送れるようになった。
ちなみに、1万年前の人類が摂っていた糖質は、1年間でわずか小さじ22杯であったといわれている。
それが現代ではどれくらいになっているか想像してみよう。
なんと、1年間で約63kg、小さじ21万1400杯もの糖質を摂っているのである。
これがカラダに良い影響を与えるわけがないと筆者はいう。
糖質を摂るデメリットのいちばんに挙げられるのは、 インスリンのスパークである。
これにより、血糖値が一気に上がり、一気に下がる。
さながら、ジェットコースターである。
この上下動によって、食欲のコントロールが難しくなり、ドカ食いなどが起きてしまう。
もうひとつの問題は、野菜や肉、魚など、ほかの食品と比較して、微量栄養素が不足していることが挙げられる。
そのため、カラダは満腹感が得られづらく、「もっと、もっと」と飢餓感を感じ、食べ続けることになる。
脳に「お腹いっぱい」と指令を送る「レプチン」という満腹ホルモンがあるが、これは、脂質やタンパク質を摂ったときはさかんに分泌されるが、糖質の場合はあまり反応しないという。
そして、糖質を摂取することで、なんといってもデメリットが大きいのが、「炎症」である。
その炎症を引き起こすのは、「AGE」と呼ばれる極めて破壊的な物質である。
AGEは糖質がタンパク質とくっついて熱が加えられることで出来るという。
たとえば、脳や心臓に血栓が詰まると、脳梗塞や心筋梗塞を起こすが、この血栓の原因も元を正せば、AGEによる細胞の攻撃によって生じた炎症なのである。
そして、還元していくと、その炎症も、そもそもの始まりは糖質の摂りすぎが招いた結果と言えるのである。
一昔前は脂質が太る原因とされてきていたが、実は肥満の真犯人は「炭水化物」と「砂糖」なのであるという。
ここに面白い調査報告がある。
2013年4月にハーバード大学が行ったもので、 12週間にわたって、炭水化物をたくさん食べ続けたグループと、炭水化物はほとんど食べず、脂質を含む食べ物をたくさん摂り続けたグループとで、体重の変化を比較したのである。
摂取カロリーだけを比較すると、脂質の多いグループのほうが、2万5000キロカロリーも多くなっていたのに、体重を比較すると差がほとんどなかったという。
つまり、カロリーもアブラ(脂質)も太る原因ではなかったのである。
「太る」原因は、炭水化物や砂糖といった糖質の食べ物にあるのである。
炭水化物や砂糖は体内に入ると、すぐにグルコースに変わり、インスリンを介して細胞に届けられるが、限度があるので、血流にダブついてしまう。
そんなダブついたグルコースの行き先が脂肪細胞である。
ここでグルコースは脂肪酸に変わり、体脂肪として蓄積する。
そして、それが積もり積もっていった結果、太っていくこととなるのである。
簡略化してしまうと、
〈炭水化物・砂糖〉→太る
〈脂質だけ〉→太らない
〈脂質〉+〈炭水化物・砂糖〉→太る
アブラで揚げたドーナツがなぜ太るのか、その理由がこれでわかると思う。
企業にとって、炭水化物などの糖質の食品は、安く作ることができて、マージンが高い。
そのうえ中毒性があるので、食べれば食べるほど依存するようになって、その食品はどんどん売れる。
その結果、多くの人たちが糖質中心の食生活の犠牲になっているのが現代であると筆者はいう。
確かに、外出時に昼食に何を食べようと考えた時に見渡せば、選択肢はほぼ全部といっても過言ではないほどに、糖質中心のメニューしかないのは、そういうことなのだと思う。
「良いアブラ」があなたを救う
現代には、逆に脂質=悪者のイメージが定着してしまっている。
しかし、脂質はカラダの中で実にたくさんの使い回しができる栄養素なのである。
ホルモンや酵素の材料になるだけでなく、細胞膜にも使われるし、脳内の神経伝達物質にもなる。
「良いアブラ」をちゃんと摂ると、細胞が元気になり、内臓の働きは良くなるし、皮膚や髪も美しくなる。
脳の働きもクリアになって、記憶力や集中力も増す。
アブラの摂取によって、満腹ホルモンである「レプチン」が分泌され、それによって食べ過ぎが防げて、肥満にもなりにくくなるのである。
そして、アブラを摂るいちばんのメリットといえば、それは、病気の原因となる「炎症」を防ぐことにあるという。
ここで言う炎症とは、「慢性炎症」のこと。
カラダの中で、炎症がずっと続けている状態である。
ほとんどの病気はこの慢性炎症から始まる、といっても過言ではないという。
病気を防ぐには、いかにカラダの中で慢性炎症を起こさないようにするか、ということにかかっているのである。
そして、慢性炎症のいちばんの原因は「食べ物」にある。
「良いアブラ」を摂ることで、細胞レベルで機能が上がり、毒素の排出能も高まる。
細胞は常に生まれ変わっているのである。
カラダの75%は1ヶ月で入れ替わり、95%は1年でフルチェンジすると言われている。
脳の神経細胞のように7年近くかかるものもあるが、少なくとも、1年間、良い食事をして、「良いアブラ」を摂り続ける。
そうすれば、カラダはほぼ完全に健康的な細胞に入れ替わるという。
今や日本人の2人に1人はがんになり、3人に1人ががんで亡くなっている。
これはアメリカよりも多いという。
また、心臓病で亡くなる人も3人に1人である。
また、うつ病やアルツハイマー病にかかる人も増えており、「日本の病院や製薬会社、がんセンターは商売繁盛である」という特集がイギリスの週間新聞『エコノミスト』で組まれるほどだという。
その原因は明らかに「日本の食事」にあると筆者は言う。
「アブラ」に対する意識が低いことが根底にある。
これまで、医学界では、がんは遺伝的な要素が強いと考えられていた。
しかし、最近の流れは、
「環境を変えることで、病気は防げる。遺伝子は大きな要素ではない」
という考え方にシフトしているという。
環境の中でも、特に大きな影響を及ぼすのが、食事であるから、俄然、食事と病気との関連に注目が集まるようになっているのである。
もし、あなたががんの弾を持っていたとしても、あなたが引き金を引かなければ、がんになる恐れはないと筆者はいう。
これは、「エピゲノム」という考え方に根差している。
環境や食事を変えれば、ピストルの弾倉にがんになる弾がこめられていたとしても、あなたはピストルの引き金から指をはずすことができる。
そして、ここでもっとも重要な要素が「細胞膜」である、と筆者は断言する。
「遺伝子は細胞の核の中に入っているが、その核も膜でできている。だから膜の状態こそがすべての鍵を握っている。膜が最適な状況にあると、良い遺伝子も発現する(スイッチがオンになる)」というわけである。
要は、自分を生かすも殺すも、結局は「アブラ」次第なのである。
「良いアブラ」とは何か?
アブラの中でも特に大切なのは、カラダの中でつくることのできない〝必須脂肪酸〟である、オメガ3、オメガ6、この2つであるという。
そのほかの脂肪酸は、人間のカラダがその量を調整して自らつくり出せるが、上記2つは食べ物から摂る以外に方法がないのである。
そして、摂取する上での理想の割合は、
オメガ6:オメガ3=4:1、
といわれている。
しかし、現代においては、普通に食事を摂っているだけでは、極端にオメガ6に偏りやすい傾向にあるという。
アメリカの場合だと、オメガ6:オメガ3の割合は40:1くらい。
日本でも、食の欧米化に伴い、これに準じた数値になっていると推測出来ると筆者はいう。
オメガ6に偏った食事は、体内に炎症を引き起こし、カラダに悪影響をもたらす。
では、「悪いアブラ」とはいったいどんなものか?
筆頭は、「トランス脂肪酸」。
その代表は、マーガリンやショートニングといったものである。
これらは、非常に安価につくることができるため、菓子やケーキ、パンなどに多用されている。
アメリカやヨーロッパなどをはじめ、その危険性から禁止する措置に踏み切っている国も出てきているが、日本では未だ野放しの状態だというから恐怖を覚える。
トランス脂肪酸に負けず劣らないのが、「サラダ油」や「キャノーラ油」だという。 こうしたアブラは化学的な加工度が高いため、それにつれて毒性も上がっていくのだという。
オリーブオイルやココナッツオイルなど、できる限り加工がされていない、自然の状態に近いものを選ぶのがベストであるという。
「良いアブラ」の選び方のポイントは、 なるべく加工のプロセスが少ないもの、遺伝子組み換えではないもの、バターやラードといった動物性のアブラであれば、穀物のエサを食べていないグラスフェッドの動物からつくられたものを選ぶといったことがポイントだという。
そして、迷った時は「ギー」がおすすめだという。
ギーは、インドなどの南アジア諸国で古くから食用に使われてきた乳脂肪製品で、牛乳を乳酸発酵させてできたバターをゆっくり加熱し、溶け出た脂肪分が黄金色に、沈澱した固形分が褐色に変わったタイミングで濾過して作られる。
バターよりも健康的で、長期間の保存にも耐えられるメリットがあり、2014年にはアメリカの自然療法協会が発表した「カラダに良いアブラ・ベスト5」で堂々のナンバーワンに選ばれている。
だからといって、特定のアブラに固執するのはいけないと筆者は念を押している。
複数の種類をバランスよく組み合わせて摂ることが大事なのである。
じゃあ、どういうバランスで組み合わせればいいのか?
それは次のような4種類である。
・ギー(あるいはグラスフェッドバター)[飽和脂肪酸]
・バージンココナッツオイル(あるいはMCTオイル)[飽和脂肪酸]
・エキストラバーキンオリーブオイル[不飽和脂肪酸・オメガ9]
・亜麻仁油(あるいはヘンプシードオイル)[不飽和脂肪酸・オメガ6&オメガ3
これらを偏りなく、目安として、1日の合計で男性なら大さじ8-10杯、女性なら6-8杯。 グラムにすると、1日当たり男性は120-150g、女性は90-120g。
直接摂る以外に、食材からもアブラを補うことができるため、1日3食として、料理に直接かけたり、混ぜたりして摂るアブラの量は1回の食事にだいたい大さじ1-2杯で十分だという。
そして、理想として、運動の2時間後にアブラを摂るのが効果的であるという。
運動後1時間半のタイミングで出る成長ホルモンの割合は、通常時に比べて男性で2000%、女性は1500%にも及ぶ。
その成長ホルモンが脂質をエネルギーに変えるから、その時間がベストなのである。
想像を超えた人生を実現する
「シュガーバーニング」から「ファットバーニング」への移行をより効果的に、確実に加速させる方法があるという。
それは21日間の「プチ断食」チャレンジ。
それは、 8時間の間に3食(脂質多め、糖質控えめ)を食べる。
残りの16時間は、水やお茶以外は何も食べない状態にする。
これを21日間続けるのである。
食事の量自体は、考える必要はないという。
糖質を控え、「良いアブラ」を積極的に摂り、野菜やタンパク質をきちんと摂っていれば、あとは好きなものを、好きなように、好きなだけ食べてかまわないメソッドなのである。
食べる時間を制限し、その中で糖質を控え、「良いアブラ」は積極的に摂る。
多少の制限さえ受容できれば、食べることを十分に楽しむことができるのではないだろうか?
「シュガーバーニング」の状態で砂糖を断つと、禁断症状のように、甘いものが無性に食べたくなるのは自然の反応だという。
けれども、「ファットバーニング」への移行期を過ぎてしまえば、甘いものはまったく欲しくなくなるので、そこはガマンのしどころ。
どうしてもというときは、砂糖の代わりにキシリトールやステビア、エリスリトールなどの人工甘味料を使ったものを食べるとよいという。
ただし、これらはあくまで緊急的なツール。
炭水化物、砂糖は「原則、断つ」と決めておくのが結局、いちばん楽だと筆者は言う。
しかし、習慣を急に変えることは難しいから、段階的に米やパンなどの炭水化物の量を減らしていき、徐々にルールを増やしていくのがいいらしい。
炭水化物を摂らなくも平気なのかと心配する人がいるが、本来、私たちのカラダは、野菜や果物、肉や魚からほんの少し炭水化物を摂るだけで十分に健康的に生きていけるという。
21日間のプチ断食を終えたあとも、最後の食事と最初の食事の間を16時間空ける、すなわち、食事は8時間の枠内に収めるライフスタイルは維持できるのが理想だという。
チャレンジの最中に、ご飯をたくさん食べてしまったり、スイーツに手が伸びてしまったり、夜中にラーメンを食べてしまったりしても、決して自分を責めてはいけないと筆者はいう。
多少、レールを外れても、なぜ自分がそうしたのか、冷静に原因を見つめて、そこから学べばいいのである。
ベイビーステップで、少しずつできるところから変えていけばいいと筆者は励ましてくれる。
完璧をめざす必要はない。
まずは目の前の甘いお菓子を控えてみる。
明日1日、間食をやめてみる。
今日、会社の帰りに「良いアブラ」を1つ買ってみる。
こうした小さな1歩の積み重ねが人生を変えることになると筆者はいう。
本書を通して、本来、私たちのカラダにインストールされている「ファットバーニング」の状態をメインに、そして、「シュガーバーニング」の状態をサブシステムにするという自然な仕組みを取り戻そう。
一度、経験してみると、カラダが軽くなり、脳もクリアになり、一段階アップデートしたような感覚を味わうことが出来ると思う。
そして、その状態を自由自在にコントロールする術を手に入れ、ハイパフォーマーとして、自分のやりたいことに向かってバリバリと働いていこうではないか。
このブログを読んで、本書に興味が沸いた人は是非、一読をおススメする。
きっと、読み終わった後で、ベイビーステップとして、近所のスーパーやネットスーパーで良いアブラを購入したくなることだろう。




コメント