どうも、WELLNESS INVESTMENT CLUBのtoshiです。
金を稼ぐために健康を害し、
ダライ・ラマ
今度は病を治すために、稼いだ金を使う。
将来の心配ばかりをして、現在を楽しむことをしない。
その結果、人々は現在にも未来にも生きていない。
あたかも人生が永遠に続くかのように生きているが、
真の意味での人生を全うすることなく死んでいく
これは、わたしが尊敬するダライ・ラマの箴言である。
3分で世界の見え方が変わる。
「食」は自分への投資である。
口にするものは全て、自分への投資へと繋がっているのである。
人生100年時代において、本当に必要なものとは、健康である。
それでは、本日のthree minutes investmentはこちら
牧田善二医師の「医者が教える食事術2 実践バイブル」である。
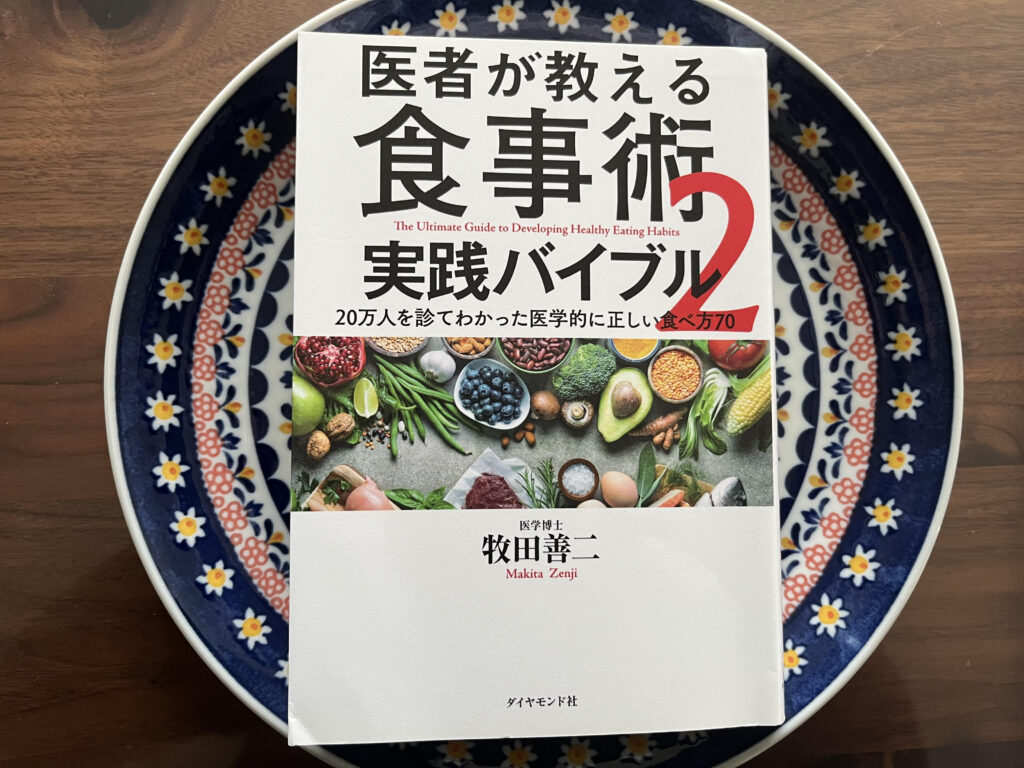
現代は健康のためには「食のリテラシー」が必要な時代となった
エビデンスによると、
「肉を食べると、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上がる」
「糖質制限によって寿命が縮まる」
「糖質制限は日本人には体質的に合わない」
「低脂肪の食事を心がけることで長生きできる」
「肥満の原因はカロリーの高い食事にある」
こう聞くと、いかにもそれっぽく聞こえ、正しそうに思えるが、
実は、これらは全て、最新の研究で否定されているものなのである。
「エビデンス」とは日本語で、根拠とか証拠、裏付けといった意味合いがあり、その言い回しはいかにもっぽく見えてしまうが、エビデンスの基となる論文もピンキリで、世界的に信用度が高いのはごく一部にすぎないという。
健康で長生きするためには、巷の情報への正しい判断力を持ち、感情的にならずに冷静に対応する「食のリテラシー(適切に理解・判断する能力)」が必要なのである。
そして、その拠り所となるのが
「生化学」
であると筆者は断言する。
例えば、美容や健康のためにコラーゲンのサプリメントがいいといった広告が雑誌やテレビのCMから流れてきて、体に良さそうに思い込んでいるが、あれなんかは典型で、「生化学」においては、コラーゲンは口から摂取してみたところで、消化・吸収の過程でただのアミノ酸に姿を変えてしまい、そのまま肌に届くことなどありえないのである。
肌に塗っても同じで、吸収されることなどなく、肌のコラーゲンとして使われることはまずないという。
また、コンドロイチンやグルコサミンが入ったサプリメントが膝や関節の痛みに効果的と大々的に広告で宣伝されているが、あれなどは、もっとも被害報告数が多いというから驚きである。
一流医学雑誌の報告では、これらは「膝や股関節の痛みや機能に対してはまったく効果がない」とはっきり結論付けられてるという。
筆者は現在、東京・銀座で糖尿病専門のクリニックを開業しており、これまでに延べ20万人以上の患者の治療に当たるのと並行して、研究者としても活動を続けているという。
その臨床において、患者と関わる中での膨大な実証データの蓄積と研究での生化学の知識と日々、最新の情報を読み解くという蓄積の相乗効果が筆者の強みであるという。
そんな筆者が行き着いた、「医学的に正しい食事」とは、
「人類のDNAに沿った自然な食べ方」
にあるという。
具体的には、「縄文人の食事に近づけること」である。
しかし、現代において、縄文人とまったく同じになどできるはずがない。
要は少なくとも、農耕によって得られる炭水化物や産業革命後に出回ったファストフードやスナック菓子、コンビニ食のような不自然な食べ物を減らしていくことが必要だということである。
これが、あらゆる病気の根本的な原因であるから。
類人猿のような人類の祖先の誕生から約600万年、人類誕生から約250万年という長い歴史の中で、糖質を安定して食べられるようになったのは農耕が生まれた約1万年前からである。
ましてや、大量摂取するようになったのは、この数十年という極めて最近のことなのである。
戦後約70年という現代において、糖質の大量摂取と約40兆円にも及ぶ国民医療費の増大はとても示唆的である。
健康で長生きするために必要な食習慣の一丁目一番地は、
「糖質を減らす」こと
これに尽きるといっても過言ではないのではないだろうか?
現代社会に暮らす私たちが、「健康のために何を食べたらいいか」を考える時には、まず、「何を食べたらいけないか」という視点が必要になるという。
例えば、巨大食品メーカーは味覚や嗅覚を専門とする科学者たちを社内の中核に擁し、その知識を用いて、「糖質」の中毒性を利用して、「繰り返し買わずにはいられなくなる」ための科学的加工をあの手この手で施している。
私たちの脳には、「チャンスがあれば糖質を摂取せよ」というプログラミングがある。そして、糖質を摂取して血糖値が急上昇すると、セロトニンやドーパミンといった脳内物質が分泌され、ハイな気分になるため、中毒に陥りやすくできているのである。
食品メーカーはそうした人間の生理を上手く突いてくることを認識すべきなのである。
本書では、何度も繰り返しふれられているが、
「現代人の肥満の原因は脂質ではなく、糖質の摂りすぎ」
口から食べた脂肪はそのまま体につくわけではなく、糖質を摂取することで、血中に増え過ぎたブドウ糖が、インスリンの働きによって中性脂肪として蓄えられる。
これは生化学をもってすれば自明の理なのである。
私たち現代人のプログラム内容は、縄文時代に生きた祖先と変わりない。
ファストフードはもちろん、多量の白米やパンや麺類、菓子、清涼飲料水などを受け付けるようには出来ていない。
そもそも、人類のDNAが完成されたときの食事は糖質制限そのものだったのであるという。
それなのに、農耕技術の発展に加え、食品メーカーという進化の権化のような存在の出現により、多くの人が「糖質中毒」に陥り、「進化的ミスマッチ」が起きているのである。
それを今更、後戻りすることなんて出来ないから、その本質を見抜き、対応していく能力を身につけることで、現代を大いに謳歌しようと筆者は述べている。
医学的に正しい「食の授業」
皆さんは「バランスの良い食事」というと、どのような食事を思い浮かべるだろうか?
ちなみに厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準(2015年版)」によれば、最適なエネルギー摂取バランスは、炭水化物から50~65%、脂質から20~30%、タンパク質から13~20%となっている。
単純に計算してみると、例えば、1日に2000キロカロリーを必要としている人の場合、炭水化物250~325g、脂質45~67g、タンパク質65~100gくらいを食べると良いということになる。
しかし、この配分が「バランスがいい」とは到底思えないと筆者は言う。
まず、脂質であるが、脂質は体にとって、とても重要な使い道がある一方で、炭水化物はエネルギー源としてしか使い道がなく、余った分はすぐに脂肪に作り変えられてしまう。
こうしたことから、脂質はもっと増やし、炭水化物は減らすべきだと筆者は提案する。
理想的には炭水化物は1日あたり120g、痩せたい人は60gにまで減らしたいところだという。
現在は朝昼晩と、ご飯やパン、麺類を食べ、ほかにもおやつにケーキやスナック菓子を食べていたら、簡単に炭水化物量は300gを突破する。
意識せずに普通に生活してるだけで、すぐに糖質過剰に陥る時代なのである。
「やせたい」、「ダイエットしたい」というのなら、その逆をやっていくしかないという。
糖質の摂取をひかえると、肝臓や筋肉の細胞に備蓄されているグリコーゲンがブドウ糖に戻され、エネルギーとして使われる。
それでも足りない分は、脂肪細胞に取り込まれた中性脂肪が脂肪酸に分解されて、エネルギーになり燃やされる。
ここまできて、やっとやせるわけである。
ちなみに、ダイエットすると筋肉も落ちてしまうのではないかと心配する人がいるが、エネルギーとしては脂肪を先に使い、タンパク質は最後なので、脂肪がまったくなくなってしまうまでは、決して、タンパク質は使われずに、筋肉は落ちないのである。
「脂肪を食べたら太る」というのが嘘であるのは、生化学的に論破が可能なのである。
そもそも、脂質は37兆個もある人間の細胞を作るのに欠かせないもので、細胞膜はリン脂質という脂肪によって作られ、絶えず作り変えられているために、脂質はそれだけ必要とされる栄養素である。
加えて、各種ホルモンの材料にも使われる。
そして、統計的に見てみると、私たちはそんなに思ったほどは脂肪は摂っていない傾向にあり、また、脂質には吸収されにくい性質があるために、大量に食べても体内に摂り込むのは難しいのである。
以上から、脂肪は太る理由にはならないのである。
筑波大学などが行った研究に関する論文によると、肉をたくさん食べ、飽和脂肪酸摂取量が増えるほど、血圧は下がっているという。
また、飽和脂肪酸の摂取量が一番少なく、炭水化物をたくさん食べている人たちに、脳卒中と心筋梗塞が圧倒的に発症しているという。
「欧米人のように肉ばかり食べていたら、循環器を悪くする」という心配は逆なのである。
心筋梗塞や脳卒中を減らすためには、日本人はもっと肉を食べる必要があるという。
しかし、肉は出来るだけ「鶏」を食べるのがいいという。
牛肉や豚肉、加工肉は大腸がんのリスクが高い傾向にあるのである。
筆者が提案する食べ方として参考にしたいのが、
魚と交互に肉を食べ、しかも鶏肉を多く、豚肉はほどほどに、牛肉はたまに、というサイクルを組むというものである。
次にタンパク質を見ていこう。
筋肉をつける目的で、運動後にプロテインを補助的に飲むのはいいことだと思っている人は多数いると思う。
しかし、本来、よほどのアスリートでない限り、運動したからといって、タンパク質の摂取量を増やす必要はないという。
ましてや、プロテインという不自然な形での摂取は尚更である。
私たちの体には、「アミノ酸プール」というメカニズムが働いており、筋肉や血液中に常に溶けた状態でプールされている。
だから、どんどん摂らなくても、すぐには大変なことにはならないのである。
タンパク質の摂り過ぎは、メリットよりもリスクのほうが大きいと筆者は警笛を鳴らす。
そのリスクとは、過剰摂取による慢性腎臓病である。
ちなみに、現在、日本にはなんと1330万人の慢性腎臓病の患者があり、2017年時点で約33万人以上が人工透析を受けているという。
これは、台湾に次いで世界第2位の数字である。
プロテインを飲むのはやめて、楽しく美味しい食事から、タンパク質を摂取しようと筆者は提案する。
遠い祖先の食事に思いを馳せると、食べ物にはあまり手を加えないほうがいいはずである。
人間のDNAに沿った食べ方
◎手を加えないほうがいい
最近、「超加工食品」が健康に与える害についての研究が増えているという。
超加工食品とは、菓子パン、スナック菓子、カップ麺、冷凍ピザなど、とくに加工の度合いが高い食品のことを指す。
パリ第13大学は、10万人以上を2009年から追跡した結果、超加工食品の摂取量が多いほど、がんにかかりやすいことを突き止めているという。
◎「五大栄養素」の働き
人間にとっての基本となる「五大栄養素」とは、糖質、脂質、タンパク質、そして、ビタミン、ミネラルを指す。
その中で、現代人は糖質を摂りすぎているため、より健康になりたいないなら、「今よりも減らす」ということを心がける。
逆に、脂質は細胞膜の原料となるなど、人体にとって非常に重要な働きがあるので、「今よりも増やす」を目安にする。
タンパク質は筋肉や骨など体を作る栄養素である。
肉、魚、卵、大豆製品などに多く含まれている。
こうした食品から自然に摂るべきであって、プロテインにような不自然なものに頼るできではない。
大雑把に言って、ビタミンは、肉や魚、野菜に多く含まれている。
ミネラルは、魚介類や海藻、野菜などに多く含まれている。
つまり、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルを過不足なく摂っていくためには、炭水化物量を減らし、おかず類を増やしいくべきなのであるという。
◎青魚を毎日食べる
魚にはオメガ3系の油であるEPAとDHAが豊富で、中でもサバ、アジ、サンマなどの青魚に特に豊富に含まれているという。
動脈硬化やがんのリスクが下がり、長寿傾向にあることもわかっているという。
◎卵は「ちゃんと食べる」ほうがいい
卵はコレステロール値を上げがちという認識が古くからあるが、最近の研究によると、豊富な栄養素が含まれ、老化の抑制も期待できるなどと、まれに見る優秀な食品であり、1日2〜3個までなら、むしろ「ちゃんと食べたほうがいい」とされている。ただし、鶏の成育環境にはこだわったほうがいいという。
価格の安い卵は狭い鶏舎に閉じ込められて、化学的なエサを与えられており、栄養価も低くなっている可能性があるのである。
◎野菜は1日350gを食べる
野菜は体を整え、快調に動かす「潤滑油」となることから、積極的に摂りたい食材 である。
1日350gを目指したい所であり、その中でも、迷ったら「アブラナ科の野菜」がおススメであるという。
代表的なのはブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、白菜、クレソン、ルッコラ、青梗菜などである。
スルフォラファンという成分が血糖値を下げる、がんのリスクを減らすなどということ効果から注目されているという。
そして、「旬のもの」を食べるように心がけよう。
旬の野菜は栄養が豊富であるのである。
調理法も大事で、基本は生でそのまま食すのがいい。
加熱調理の過程で多くの栄養素が失われてしまうからである。
もし、加熱する時は、炒めるよりも茹でる、茹でるよりも蒸すといった調理法を優先したいところである。
◎大豆はとにかく最強食材
豆腐などの大豆製品は、欠点が見つからない完璧な食材の一つであるという。
抗酸化作用、がんのリスク低減、ダイエット効果などと枚挙に暇がないのである。
そして、納豆である。
発酵食品として優れた整腸作用だけではなく、その成分のナットウキナーゼは血栓分解効果があり、脳梗塞の予防になるという。
筆者のおすすめは朝ではなく、夜に食べるほうがいいという。
脳梗塞を引き起こす血栓は深夜から朝にかけてできることが多いという理由からである。
◎小腹が空いたら30gのナッツを食べる
ナッツは血管性疾患のリスクを減らす、コレステロールや中性脂肪を減らすといったような効果があり、世界中から「体にいい」とお墨付きを得ている。
間食も医学的に賢く摂取していきたい。
◎質のいいオリーブオイル
質のいいオリーブオイルは血管性疾患のリスクを減らす、血中コレステロール値や中性脂肪値の改善、糖尿病の予防などにもつながるという。
質にはこだわりたいところで、信頼できる店で売られているエキストラバージンオリーブオイルで、できればコールドプレスという熱を加えない状態で搾ったもので、冷蔵輸送か温度管理されたものを選ぶのがおススメであるという。
◎ご飯を食べる前に「タンパク質」を摂る
ご飯やパンなどの炭水化物は、タンパク質や脂質、食物繊維と一緒に食べることで、血糖値の上昇が抑えられるという。
まずは、肉や魚といったタンパク質のおかずを食べ、次に小鉢の野菜を食べ、なるべく最後にご飯を食べるようにする習慣をつければ、糖尿病の予防につながるのである。
一にも二にも血糖値コントロール
1972年にある画期的な本が刊行されている。
近藤正二医師が書いた、
『日本の長寿村・短命村』
という本である。
近藤医師が1935年から36年間もの歳月をかけて日本中を練り歩き、長寿の村や短命の村の生活様式を調べた結果をまとめたものである。
その結論の1つが、
「ご飯(白米)をたくさん食べている村は短命」
ご飯をたくさん食べれば、血液中にブドウ糖が溢れ、血糖値が上昇し、結果、健康を著しく害すことになるのである。
健康維持のために、血圧には普段から気をつけており、健康診断でもその値には特に敏感であるとか、毎日、自宅で血圧を測定しているという人もいると思うが、今はそれ以上に「血糖値」が重要な指標となっているという。
血糖値が高いと、肥満を呼び、あらゆる生活習慣病にかかりやすくなるのである。
さらに、老化促進物質である「AGE」と呼ばれるものも生成される。
このAGEとは、血液中にブドウ糖が多い(血糖値が高い)ことで生成される有害物質で、体内に多くできると炎症を起こし、その組織をボロボロにしていき、体中の細胞に悪さをし、その害は、糖尿病の合併症だけに留まらず、がん、心筋梗塞、脳卒中、アルツハイマー病など、ありとあらゆる疾患の元となるという。
それだけではなく、シミやシワなどの老化の原因にもなるという極悪なものなのである。
そういったことから、現代は、
「血糖値コントロール」
こそが喫緊の課題であるという。
そして、血糖値は、食事に対する正しい知識さえあれば自分でコントロールが可能であるという。
そのためには、本書に書かれているテクニックを身につけ、食のリテラシーを高める必要があるのである。
筆者が毎日、臨床において多くの患者を診る中で、
「仕事で成功するよりも、お金持ちになるよりも、健康で長生きすることが一番大事」
であるという気づきを得たという。
私たちを脅かす病気の多くは、私たちの生活がつくりだしている。
そして、特に食事が与える影響はとても大きいのである。
何をどう食べるかという「術」によって、体はまったく変わるのである。
本ブログを読んで、本書に興味が沸いた人は是非、一読、いや、穴があくほどに熟読することをお勧めする。
本書を最大限に活用することで、一人でも多くの人が真の健康を手にすることが出来ると確信している。




コメント